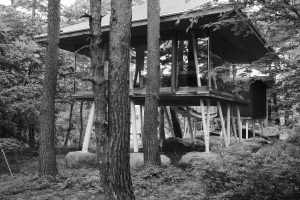ノルウェーで訪れたSnøhettaの働き方に興味が湧いて、僕は4つの質問をした。
Q1/「デザインはどう始まるか? デザイン決定権は誰にあるか?」
・プロジェクトが決まるとチームを編成する。プロジェクトの規模によるが、基本的な編成はDirector 1人とArchitect 3人。Directorの役割は、予算やスケジュールをほかのメンバーに明確に伝え、日々管理するPM業。Architectは、3人のうち1人がチーフとなって、残り2人がそのサポートをする。
・デザインの進め方にルールやルーティンはないが、デザインの話をするとき、メンバーの口からは、「connect」という言葉が何度も何度も出てきた。
・プロジェクトに「誰をどうアサインするか?」「プロジェクトの最も大切なことは何か」「最終的に何を成し遂げるのか?」「この建築によってどんな世界をつくるか?」など、物理的、実需的な議論の前に、叶える世界とつくることの責任、そして誰と一緒にやるかを時間をかけて議論すること。それを「connect」と呼んでいた。
・デザインに関することのみならず、知財のconnect、未来へのconnect、責任のconnectなど、プロジェクトの周囲にある物事を洗いざらい予測して、徹底的に議論し尽くす。
・デザインの最終決定権は、もちろんSnøhettaのボスにある。しかし、例えば、ボスが「このデザインは好まない」と言っても、connectがあるおかげでボスとチームはconnectを中心に議論する。だから、すべてがひっくり返ることにはならない。
・日本の設計事務所では、トップの一声でデザインがひっくり返されることもよくあるが、Snøhettaではプロジェクトの根っこにあるconnectについてメンバー全員が理解しているから、そんな事は滅多に起きないそうだ。
Q2/「Directorの役割は?」
・基本、DirectorはPM業務を兼ねる。
・スケジュール管理やコスト管理、クライアントのやりとり、そしてArchitectチームとの情報連携もDirectorの仕事。その良し悪しがプロジェクトの成否を決める重要なポストで、プロジェクト全体について手に取るように理解している高いスキルとリテラシーが求められる。
・優秀なDirectorは、一人で何プロジェクトも担当するといい、彼ら彼女らが持つ高いリテラシーフィルターを使い、その言葉が動力となってプロジェクトを前に進める。
Q3/「プロジェクトの原価・設計や工事コストの管理は?」
・これもconnectが重要だという。最初に、絶対に譲れないコアを決めてコストを積算する。そして、残った予算をほかの要素に振り分ける。
・構造を見せたいプロジェクトでは構造にしっかりコストをかけ、仕上材のコストを落とすなど、ケースバイケースで判断する。
Q4/「Snøhetta社員が共通して大切にしていることは?」
・「建築とデザインが持つ機会と責任」と答えてくれた。「いかに社会的にインパクトを生み出せるか、」「ウェルビーイングや自然との近さ」「建設および設計プロセス全般における健全で平等な労働」、そして、「責任ある建設や環境負荷の低減」「人と動植物が共存できる場の創造に挑み続けること」をチーム全員が大切にしているという。
最後に、あらゆるポジションのメンバーがプロフェッショナルとしての自覚と責任を果たすこと。
それが、いいチームの秘訣だと語ってくれた。
なんとも腹落ちするコメントだった。
やっぱりかっこいいぜ。レペゼンSnøhetta!
そろそろお腹がいっぱいになってきているだろうが、今回訪ねたオスロの「物足りない街」で感じたこと。
そして、Snøhettaのスタッフが答えてくれた4つの質問。
それらを僕なりにまとめると、ノルウェーの人々にとっての「本質的な豊かさ」に辿り着く。
ノルウェーは、国全体が「人」を中心とした仕組みで動いている(お金を稼ぐことや派手なパフォーマンスではなく)。
とにかく税金や物価が高いのは事実で、ペットボトルの水が1本500円もする一方で、水道水は安全でどこでも飲める。娯楽の税金は高いが、本には税金がかからない。
人が豊かな思考を学び、幸せになるための仕組みがそこにはあるのだ。
レストランももれなく高いので、今回の旅でも外食はほぼせず、男4人で毎日自炊した。
ノルウェー人も外食は1ヶ月1回程度。特別な時間を過ごすためという意識だそう。
毎日のように夕食を外で食べるというと、「大丈夫?」と心配されるくらいだ。
ノルウェー人にとっての理想のライフスタイルとは何か。
それは、20代でファーストホームを持ち、40代でセカンドホームとボートを買う。
そして、その場所で、家族や大切な人と少しでも多くの時間を過ごすこと。
幸せの定義が明快で、僕らより遥か先の次元を行っていると思った。
じゃあ、明日から、「僕も彼らのように振る舞えるか?」と問うと、それは難しい。
ただ、そんな世界について、もう少し真剣に考えてみるのは悪くないと思った。